|
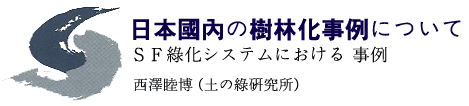
 開発によって森林が伐採され,表土が剥ぎ取られ裸地斜面(法面)が出現するということは,人類が生きていくうえで全世界同じ問題を抱えていると言える。裸地斜面の出現は,自然破壊と呼ばれるだけでなく,日本のように降雨量の多い地域においては斜面の侵食を招き,ひいては土砂流出・斜面崩壊等,防災上問題が生じる。しかし,このような箇所においては,一般に植物の導入が困難であり,この箇所に,如何に植生を復元し,国土保全・災害防止上重要な表面侵食防止を図り,自然環境を復元するかが緑化工技術と考える。 開発によって森林が伐採され,表土が剥ぎ取られ裸地斜面(法面)が出現するということは,人類が生きていくうえで全世界同じ問題を抱えていると言える。裸地斜面の出現は,自然破壊と呼ばれるだけでなく,日本のように降雨量の多い地域においては斜面の侵食を招き,ひいては土砂流出・斜面崩壊等,防災上問題が生じる。しかし,このような箇所においては,一般に植物の導入が困難であり,この箇所に,如何に植生を復元し,国土保全・災害防止上重要な表面侵食防止を図り,自然環境を復元するかが緑化工技術と考える。
さらに21世紀を迎えた現在,全世界的に環境問題が取り沙汰されている。その中でもCO2の排出量の削減において森林の果たす役割が注目されている。開発によって生じた裸地斜面に,単に森林を再生させるのではなく,生態系を復元させなければならない時代となった。
このような問題を解決すべく開発したのが,SF緑化システムである。SF緑化システムによる日本国内2万ヶ所2000万㎡を超える樹林化実績を紹介すると共に,緑化工の技術・世論の要望の変遷を以下に紹介する。
1. 日本における法面緑化工の変遷
日本においては1950年代以前は,人力による治山や砂防工事が,郷土性を持ちながら行われきた。しかし1950年代以降は,急速な開発と共に,大規模な裸地斜面(法面)が出現するようになり,機械播種工による植生復元技術(緑化工)が,その時々の要望に応じて開発され,今も開発が続いている。
機械播種工による植生復元方法の変遷を大まかに纏めると表-1、2のようになる。
表-1 機械播種工による年代毎による緑化工の要望と対応例の変遷
|
年代
|
要望
|
開発工法
|
導入植物
|
緑化時間
|
対象地
|
|
1950~
|
大規模早期全面緑化
(侵食防止機能)
|
種子散布工
|
外来草本主体
|
数ヶ月
|
盛土・切土
(土砂)
|
|
1960~
|
〃
(無土壌地での施工)
|
客土吹付工
|
〃
|
〃
|
切土
(硬質土等)
|
|
1970~
|
〃
(岩盤部の緑化)
|
厚層基材吹付工
|
〃
|
〃
|
岩盤法面まで可能
|
|
1980~
|
早期樹林化
(防災と景観)
|
高次団粒吹付工
|
木本類
|
1~3年
|
〃
|
|
1990~
|
多様な樹林化
(郷土性回復)
|
植生基材吹付工
|
郷土種
|
3年以上
|
〃
|
|
2000~
|
生態系・自然回復
(環境保全)
|
リサイクル工法
|
周辺と同様な群落
|
5年以上
|
〃
|
表-2 機械播種工の種類と特徴
|
工法名
|
使用材料
|
使用機械
|
耐侵食性
|
吹付厚
|
|
種子散布工
|
種子+木質繊維+侵食防止剤+肥料+水等
|
ポンプ
|
無い
|
1cm以下
|
|
客土吹付工
|
種子+肥土+侵食防止剤+肥料+水等
|
ポンプ・モルタルガン
|
余り無い
|
1~3cm程度
|
|
厚層基材吹付工
|
種子+有機基材(バーク堆肥,ピートモス等)+侵食防止剤+肥料等
|
モルタルガン
|
工法により異なる
|
3~10cm程度
|
|
高次団粒吹付工
|
種子+粘土+有機基材++木質繊維+団粒化剤+肥料等
|
ポンプ
|
有る
|
1~10cm程度
|
|
植生基材吹付工
|
上記の厚層基材吹付工と高次団粒吹付工等を総称
|
ポンプ・モルタルガン
|
工法により異なる
|
1~10cm程度
|
|
リサイクル工法
|
現場発生木材・汚泥などを利用
|
ポンプ・モルタルガン等
|
工法により異なる
|
工法により異なる
|


|